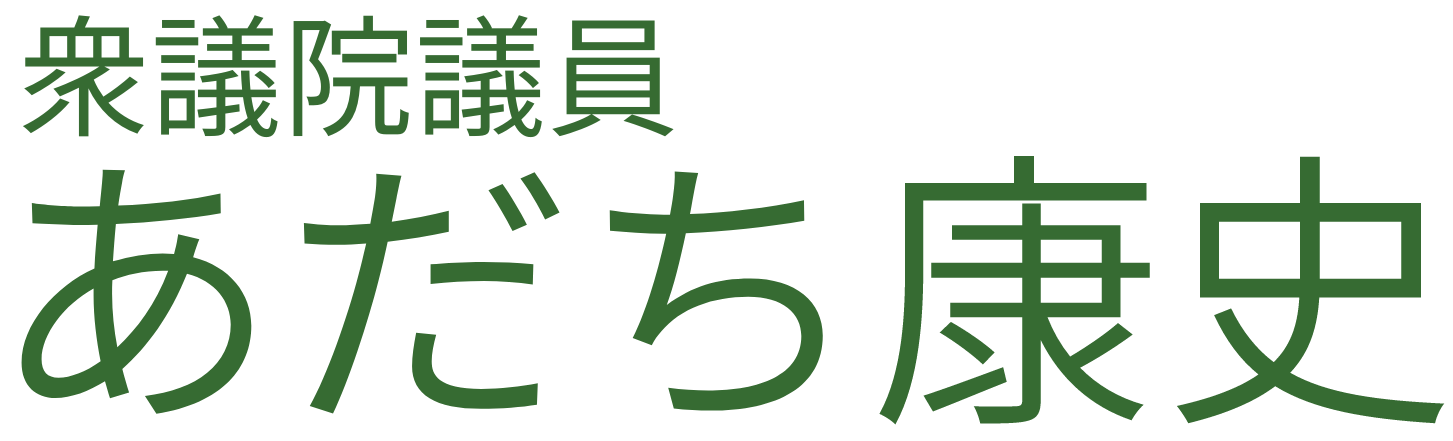民意とともに進化する新しい政治運動 ―みんなの党は政界再編に殉じるべき―
1.道州制のセンターピン -“消費税の地方税化”と“衆議院の定数半減”-
8月31日の未明、橋下市長がツイッターで次のように語りかけた。「みんなの党の渡辺代表から連絡がありました。」云々。これ自体は、その日にテレ朝で報じられた大誤報に係るツイートであったが、それに次いで、維新の政治運動の核心に触れる連続ツイートが始まった。
まず衆議院480人を240人に半減するという提案について「国会議員の皆さんから多くのご批判を頂きました。」と切り出し、最初に、自民党の「(橋下市長は)具体的な手順を示していない」との批判に対し、簡潔に手順を説明。
次に「340人の国会議員では民意が反映されない」という民主党輿石幹事長の指摘を取り上げ、民意には、1)小さいコミュニティーや特定の人の民意である“ミクロの民意”と2)国全体の民意である“マクロの民意”がある、と持論を展開。
“マクロの民意”については、国会議員が、「地方議員レベルの民意を汲む役割」をしてしまっている、つまり「盆踊り、葬式、その他地域行事に出倒す」ことで「小さな範囲の民意に拘束され」ている、と断じ、「選挙区エリアを広く(せめて現行の2倍に)して、ミクロの民意から国会議員を解放」する、と提案。そして、「ミクロの民意をくみ取るのは地方議会だ。国と地方の役割分担。」と締めくくった。
第三に、民主党の前原政調会長の「衆議院240人にすると官僚依存になる」との指摘に対しては、「官僚依存にも良いものと悪いものがある」とたたみかけ、1)「選択肢を作り、制度設計をし、実行する」という行政実務は(官僚組織にしかできないので)“良い官僚依存”、2)「官僚組織の価値観で決定・判断され、それに政治が従う仕組みになっている」のは“悪い官僚依存”、と整理。
その上で、「政治の価値判断・決定に基づいて行政が運営される仕組み」を“議員を増やすアプローチ”ではなく“行政組織の幹部を政治任用するアプローチ”で実現する、選挙で選ばれた政治家と同じ価値観・方向性を目指す専門家を官僚組織の幹部に据えれば「政治家の数が少ないからといって官僚依存になることはない」と解説した。
・―・―・
以上が民主自民・二大政党幹部からの批判に対する橋下市長の反論であるが、橋下市長のツイートはここで終わらない。
要すれば、真の意味での地方分権=道州制の実現に向け必要な、①権限、②財源、③人間、の移譲を実現するために、まず、“消費税の地方税化”によって②財源を、“衆議院240”によって③人間を移譲し、それらを先行させることによって最も困難な①権限についても「移譲せざるを得ない状況を作っていく」というのである。
道州制は、国と地方が互いに責任を押し付けあう”融合型行政”から、1)外交防衛やマクロ政策を担う国、2)広域行政を担う道州、そして3)住民サービスを担当する基礎自治体のそれぞれが自立して切磋琢磨する”分離型行政”への転換を意味するものであり、①権限、②財源、③人間、の移譲が不可欠だからだ。
結局、橋下市長は、二大政党からの批判を逆手に取って、“消費税の地方税化”に加え“衆議院の定数半減”こそが、大阪都構想の向こうにある道州制の実現に向けたセンターピンであると宣言してみせたのだ。
・―・―・
2.中央政党と地域政党 - その特徴と対話の難しさ -
私が二十年余りにわたる霞が関での勤務に終止符を打ってみんなの党の政治運動に身を投じた昨年9月8日からちょうど一年。その間、ずっと考えてきたのは、道州制を、関西州を、どうやって実現するか、という難問だった。昨年11月の大阪ダブル選挙で松井一郎知事の、今年4月の茨木市長選挙で木本保平市長の応援に駆け回っている間も、ずっと考えていたのはこのことだった。
残念ながら「道州制」という言葉は、橋下市長が「道州制なんて、いったいどれくらいの政治家が口にするか。しかしそれを本気で実行に移した政治家はいない。」と断じるように、既存政党に使い古され、単に「道州制」云々と訴えても、「何もやらないということ」だと受け止められかねない、そんな状況が続いてきた。
3年以上前に、みんなの党最高顧問の江口克彦参議院議員が中心となって「地域主権型」の道州制を提唱したのも、「道州制」の“実現しない”というイメージを払拭し、政治力を結集するための訴えであった。これまでの中央が上から目線で“分け与える”中央集権型の地方分権ではなく、地方が必要な権限・財源・人間を“奪い取る”あるいは“取り返す”地域主導型の戦う地方分権、そうした意味で「地域主権」という言葉を全面に打ち出したのだ。
そして今、橋下大阪市長が、道州制を実現するための具体的政策として“消費税の地方税化”と“衆議院の定数半減”というセンターピンを打ち出し、まさに道州制の実現に向けた「大号令」を発しようとしているのだ。みんなの党という中央の政党だけでなく、力のある地域政党が「道州制」の実現を訴える、これは統治機構を変える困難な戦いにとって、本当に望ましいことであり、だからこそ、みんなの党の渡辺喜美代表も自らのブレーンを紹介するなど一貫して大阪維新の会に対する支援を惜しまなかったのである。
・―・―・
ところが、ここに来て、大阪維新の会とみんなの党との選挙協力に向けた協議が難航していると報じられている。今月20日の橋下市長・松井知事と渡辺代表との会談についても、橋下市長のツイートで言及されており、報道は概ね事実であろう。
大阪維新の会とみんなの党との違いについては、先のコラムにおいて既に指摘してきた。みんなの党は、政策は教条主義的で政局については漸進主義的、一方の大阪維新の会は、政策については現実主義的であるが政局は急進主義的だ、と論じた。こうした政策と政局に関する整理は、ある意味で現象面を整理したものに過ぎず、なぜそういう違いが生まれているのか、については言及していなかった。
しかし考えてもみて欲しい。渡辺代表はじめみんなの党の中核メンバーは、長年にわたって国政で激しい闘争を繰り広げてきた歴戦の闘士である。国家の権力闘争がどういうものか、これまでの改革派がどのようにして骨抜きにされてきたか、を熟知している。それが故に、道州制をめぐる戦いに当たっては、そうした過去の二の舞にならないよう、焦点となる政策課題を“アジェンダ”と称し、アジェンダを同じくするグループとは連携するが、そうでなければしない、という立場を鮮明にして歩みを進めてきた。いわば“純化路線”だ。
一方の大阪維新の会は、地域政党である。しかし、ただの地域政党ではない。地方行政に携わり、昨年の大阪ダブル選挙では大阪府市の二重行政を廃する“大阪都構想”を掲げ勝利、いまでは、大阪府市の首長と(公明党の協力を得て)議会を掌握、大阪の政権を担う地域政党である。そして、大阪都構想を実現するための法律を成立させるためには国会を構成するあらゆるグループと連携し、実際、大都市地域特別区設置法は先月29日に民主、自民、公明、みんなの党などの賛成多数で成立している。
“中央の野党”であるみんなの党と“地方の政権”に就く大阪維新の会。道州制と公務員制度改革そして選挙制度改革など政策はほぼ完全に一致していても、政治的立場は間逆なのである。
・―・―・
3.新しい政治運動を勝利に導くために ―みんなの党は政界再編に殉じるべき―
先に述べたように、私たちの道州制を巡る戦いは、これまでの中央が上から目線で“分け与える”中央集権型の地方分権ではなく、地方が必要な権限・財源・人間を“奪い取る”地域主導型の地方分権であるべきである。そうであれば、ここまで進化した大阪の新しい政治運動をどこまでも尊重し、みんなの党は、中央政党としての、道州制の本家としてのプライドをいったん捨てて、大阪の新しい政治運動の成功のために柔軟に対応していく必要があるし、その責務があるのではないだろうか。
昨年11月の大阪ダブル選で松井一郎候補と戦った倉田薫前池田市長がある会合で「橋下さんは進化を続けている」と吐露されていたが、倉田さんがダブル選に臨んだ時よりも橋下さんはずっと大きくなっている、それが橋下代表と関わる政治家たちの偽らざる感想だろう。大阪ダブル選挙の焦点となった大阪都構想の向こうに、ダブル選当時はほとんど姿を現していなかった道州制の姿がくっきりと浮かび上がってきているのである。
私は、新しい政治運動が本当の意味で成功することが大事であると考えており、みんなの党の同志もまったく同じ考えであると信じている。みんなの党の結党宣言には、“我々「みんなの党」は、政権交代後の更なるステップとして、今の政党政治を整理整頓して、政治理念や基本政策ぐらい一致させた「真っ当な政党政治」の実現、すなわち、「政界再編」を究極の目標とするものである。”とあり、続けて“今後、この政界再編の荒波の中で、政党横断的に改革派を糾合する「触媒政党」の役割を果たしていけたらと思う。”とある。
「触媒政党」という言葉に象徴されるように、みんなの党は、政策軸の政界再編を“加速”させるために結党されたのであり、みんなの党が再編の主役として自己主張することは、その結党時から想定していなかったはずである。そして、既に大阪の新しい政治運動が、みんなの党の「脱中央集権」と「道州制」という政策の旗を完璧に引き継ぎ、次期総選挙の争点化に成功しつつあるではないか。
みんなの党の結党の精神が、政策軸の政界再編に殉じることなのであれば、私は、既にその時を迎えているのだと考えている。総選挙にあたって、同じ政策を掲げた二つのグループが選挙で激突し、都市部の多くの小選挙区で衝突をする、そんなことになれば、喜ぶのは二大政党=既存政党であるし、何よりもみんなの党の政策を支持してきてくれた有権者を裏切ることになる。それでは、左派勢力がかつて相争い長期的には退潮していったように、政権を担い新しい政治体制を築くことはできない。
新しい政治運動を成功させるためにも、今こそみんなの党が結党の原点に立ち戻って決断する、そのタイミングなのである。